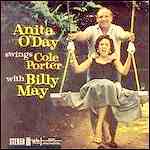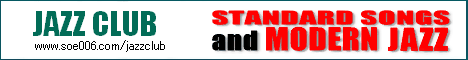Easy to Love
1936年
作詞・作曲/コール・ポーター Cole Porter
私にはよく分かっているの
貴方が私に好意をもってくれるなんて考えるの、時間の無駄だってことを
私の告白に耳を傾けるのだって、貴方にとっては煩わしいだけだってことも
でも分かって頂戴、これって私だけのせいじゃないのよ
貴方が私を惚れっぽくさせてるの
貴方が私に憧れを抱かせているのよ
二人は自然に仲良く、そして気儘にやってきたし
貴方となら暖かい家庭をつくれるかも知れない
貴方を見ていると、当然のように、そんな夢みたいな未来を想像してしまうの
だって貴方がそんな風に、私を単純に、惚れっぽくさせてるから
この華麗なメロディを持つナンバーは、コール・ポーターがミュージカル『Anything Goes』(1934年)のために用意していた曲でしたが、主演のウィリアム・ギャグストンの声に合わずお蔵入りとなり、1936年のMGM映画『踊るアメリカ艦隊 Born to Dance』に使用されて陽の目をみました。
ポーターの作品としてはまことに素直な内容で、アイロニカルでヒネたところのない、いたって平凡な歌詞です。(訳すのにはメチャメチャ苦労しましたが)
映画のなかで唄っていたのは、エレノア・パウエルとジェームズ・スチュアート。
1974年に編纂されたミュージカル・アンソロジー『ザッツ・エンタテインメント That's Entertainment!』で、スチュアートが当時を振り返りながら語っていました。「私は歌が不得意なので吹替えになる予定でしたが、曲が有名になったため、会社は私に唄うように命じました。なんとか見られる場面になっているのは、コール・ポーターの曲が素晴らしかったからでしょう」
「Easy to Love」はその後、ミッキー・ルーニー主演の『青春学園 Andy Hardy's Blonde Trouble』(1944年/日本未公開)、エスター・ウィリアムズ主演の『This Time for Keeps』(1947年/日本未公開)でも唄われ、同じくエスター・ウィリアムズ主演の『Easy to Love』(1953年/日本未公開)ではタイトルにもなっています。
歌い出しの歌詞「You'd be so easy to love」が、そのまま曲名として表記されているレコードもあるので、要注意。
フランク・シナトラのReprise設立第1弾アルバム(1961年録音)でも、「You'd be So Easy to Love」とクレジットされています。ミディアム・テンポで軽快に唄うシナトラの声には張りがあり、絶頂期(自己のレーベルを興したり、ケネディ大統領の就任祝賀パーティーを演出したり、翌62年には世界一周ツアーを挙行したり)の余裕と貫禄が伺えます。オーケストラ・アレンジはジョニー・マンデル。
定評のあるエラ・フィッツジェラルドのソングブック・シリーズ(Verve)ですが、その第1弾となったのが、この「コール・ポーター集」(1956年3月録音)でした。
コンサートでは自由奔放なアドリブで聴衆を熱狂させていたエラも、ソングブック・シリーズでは偉大なソングライターたちの作品を後世に残すことを第一義と考え、メロディと歌詞を崩すことなくストレートに歌い上げています。また、エラはシリーズ全曲で(ヴァースのあるものは)すべてヴァースから唄っています。そんな教科書的なところが、数あるソングブック・シリーズのなかでも真っ先に挙げられる要因となっているのでしょう。
エラのヴァージョンもいいけど、真面目すぎてJazzっぽくない、機知に富んだポーターらしい面白みが足りない。もっと遊び(アドリブ)のあるヴァージョンを聴きたい。そんな貴方には、アニタ・オデイをお薦めします。1959年4月録音。伴奏はビリー・メイ楽団。
他にもいろんなシンガーが録音を残していますが、コール・ポーターのナンバーは、真面目過ぎてもつまらないし、かといって泥臭いフェイクを交えて唄われると汚く聞こえてやりきれない。適度に遊びごごろを交えつつ粋に唄えるシナトラとアニタが、やはりポーターに一番適しているんじゃないかと思います。
ところで、モダン・アルト・サックスの第一人者というと、真っ先に名前が挙がるチャーリー・パーカーですが、最近は若い人たちにあまり聴かれていないようです。
いきなりバリバリと繰り出すバップ・フレーズに馴染めないのか、それとも録音の古さがデジタル・レコーディングのクリアな音質に慣れた耳に二の足を踏ませているのか?
(耳に二の足を踏ませるってのも、なんだか妙ちきりんな慣用表現ですね……自分で書いてて笑ってしまった)
そんなパーカー初心者にお薦めしたいのが、「ウィズ・ストリングス」です。ストリングス・オーケストラをバックに有名なスタンダード・ナンバーばかりを演奏しているので、もしパーカーのフレージングに馴染めなかった場合でも、(ジェームズ・スチュアートの唄のように)曲の魅力で、なんとか最後まで聴き通せることでしょう。録音も、チャーリー・パーカーのレコードとしては良好なほうです。
もちろんこれがパーカーの真骨頂ということではなく、コルトレーンの『Ballads』(Impulse!)と同様、本来の路線を逸脱したところに位置する録音なのですが、甘美な――いや、もっとストレートに言うと「売れ筋」を意識した、まるで映画音楽のようにゴージャスでダサい――ストリングスを向こうに回し、孤高のフレーズを紡ぎ出すパーカーの姿は、実に颯爽としてカッコいいです。
LP3枚分のセッション(49年11月録音/50年7月録音/50年8月ライヴ録音)からマスター・テイクだけを1枚のCDにまとめた『Charlie Parker with Strings: Master Takes』(Verve)がお買い得です。「Easy to Love」も50年7月のスタジオ録音と同年8月のライヴ録音の2ヴァージョンが収録されていて、聴き比べができます。