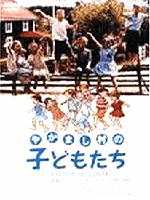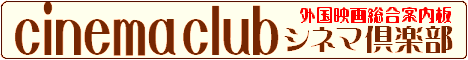やかまし村の子どもたち/やかまし村の春・夏・秋・冬
Alla A Vi Barn I Bullerbyn
Mera Om Oss Barn I Bullerbyn
1986年/スウェーデン/90分/86分 (日本公開:2000年7月)
- 製作 バルデマル・ベルイェンダール Waldemar Bergendahl
- 原作 アストリッド・リンドグレーン Astrid Lindgren
- 脚本 アストリッド・リンドグレーン Astrid Lindgren
- 監督 ラッセ・ハルストレム Lasse Hallstrom
- 撮影 イェンス・フィッシェル Jens Fischer
- 音楽 イェオルグ・リーデル
- 出演
- リンダ・ベリーストレム Linda Bergstrom
- アンナ・サリーン Anna Sahlin
- ヘンリク・ラーソン Henrik Larsson
- エレン・デメルス Ellen Demerus
- ハラルト・ロンブロ Harald Lonnbro
1927年(昭和2年)のスウェーデン。
森と湖に囲まれた静かな山村に、たった3軒が片寄せ合っている小さな集落。
そこに生活する6人の子どもたちを、素朴なタッチで描写したスケッチブック。
北欧の澄んだ空気、光や風や水を相手に、遊び、働き、生きている子どもたち。
夏休みが始まって新学期が始まるまで、大きな事件は何一つなく、長閑な時間だけがゆったりと流れる。
子どもたちの天真爛漫な動きと表情から、確かに伝わってくる自然と生命の息吹。
それがこの映画のすべて。
素直で直感的な描写に、作為は微塵も感じられない。
続編の『やかまし村の春・夏・秋・冬』と併せて、何度も(ビデオで)観ているんですが、ストーリーはほとんど憶えていません。
景色がとても美しく撮影されているので、それだけで充分心地よいのですが、そのうえこの映画には、誰一人として悪人が登場しません。みんな善い人ばかりです。
始まって5分もすると、映画を観ている意識が薄れ、いつの間にか村の住人となって、子どもたちの日常を、頬緩ませてぼーっと見守っていたりします。
学校の帰り道、だらだら道草くってばかりだった俺なんかは、もう桃源郷の心地よさ。
感受性、想像力、ユーモアは自然の営みから学ぶべきもの。
浮島で海賊ゴッコをやって怖いオジサンから怒鳴られたり、真夜中に部屋を抜け出して水の妖精を見に行ったり、干し草の上で眠ってみたり……冒険、イタズラ、好奇心、家業の手伝いもきっちりやって、おおらかで屈託もなく、遊んで働いて……子どもたちの日常は、すべて生きていることの証(あかし)。
対する大人たちの、子どもたちとの距離感も素晴らしく、とても好感が持てます。
特に、買い忘れた品物を思い出して何度も店に戻ってくる女の子たちに、その度にキャラメルの缶を開けてあげるオジサンとか、印象深いですね。このような味のある大人になれるよう、俺も努力しますですよ。
原作は、「長くつ下のピッピ」で有名な童話作家アストリッド・リンドグレーン。
えっ、原作あるの? ってことは、子どもたちはその台本に沿って芝居してるの?
……ウソだろ!
疑いたくなるくらい、子どもたちの素振りは自然そのもの。演技を感じさせません。
ストーリーは主人公の女の子リーサ(リンダ・ベリーストレム)のナレーションによって、ゆっくりと流れてゆきます。日本語吹替えもありますが、子どもたちのナチュラルな発声も肝心な部分なので、出来れば原語版で観ていただきたいなぁ。躍動感がぜんぜん違いますよ。
リンドグレーンの原作は、『やかまし村の子どもたち』、『やかまし村の春・夏・秋・冬』、『やかまし村はおおにぎわい』の3冊ですが、これをエピソード毎に分解し、夏休みの出来事をメインとした本作と、そのラストシーン(夏休みが終わって新学期が始まる)から次の初夏を迎えるまでの冬のエピソードをまとめた『やかまし村の春・夏・秋・冬』の2本が映画化されています。
脚色もリンドグレーン自身が担当。
リーサが病弱な子羊(ポントゥス)を育てるエピソードは『春・夏・秋・冬』に収録。元気に成長した子羊を学校に連れて行っちゃう場面は、子どもたちと一緒になってクスクス笑いが止まらなくなります。ただ子羊を学校に連れて行ってるだけの単純な場面なのに、可笑しくて可笑しくてたまらない。それがこの映画の偉大なところ。
イェンス・フィッシェルのキャメラは絶品! 子どもたちが真夜中に家を抜け出し、水の妖精を探しに出掛けるシーンは、森の美しさが白夜の神秘性と相まって、息を呑むほどの素晴らしさです。